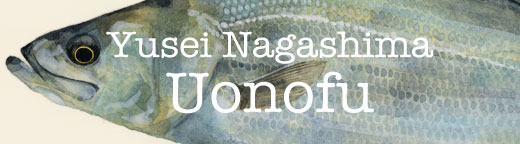温帯に戻る
石垣島にも拠点を残しつつ、東京に主軸を置いた生活を送っています。
石垣島では四六時中思い立てばいつでも気軽にフィールドに出られる暮らしでした。サンゴ礁、岩礁、砂浜、干潟、マングローブ林、湿地、渓流、漁港と、さまざまな環境で多様な生き物に触れてきました。
もはやそのような暮らしは望むべくもない…という一種の覚悟とともに東京に戻り、ある面においては確かにその通りであるわけですが、一方で「思っていた以上に身近にいろんな魚がいる、それも亜熱帯の環境に慣れた目にはとても新鮮に映る魚たちが」という驚きと喜びを新たに感じてもいます。
2024年夏の個展のテーマにも設定したように、石垣島では「多様な環境で身近に出会える魚」としてアベハゼ属の魚たちに執心していました。しかし、東京で見られるのはアベハゼ1種のみ。出会うには淡水と海水とが混じり合う汽水域を求めて河口付近に赴く必要もあります。

それに代わり、近頃はウキゴリ属のハゼたちを追うようになりました。淡水域にはウキゴリやスミウキゴリ、ジュズカケハゼ、ムサシノジュズカケハゼなどが、汽水域にはビリンゴやニクハゼ、チクゼンハゼなどが棲んでいます。石垣島での移動のように気軽にはいきませんが、都内各所を巡るうちにさまざまな環境に出会い、そこに息づくかれらに触れることができるようになってきました。
ウキゴリ属のハゼたちが面白いのは、その種や環境の多様性に加え、多くの種のメスが早春から春にかけて婚姻色を呈するという季節性です。石垣島の生き物たちにももちろん季節性はありますが、少なくともアベハゼ属に関しては目立って感じることはありませんでした。いまウキゴリ属の魚たちを見ていると、改めて四季を有する温帯の美しさを実感します。





以下はウキゴリ属を求めてのフィールドで出会う、その他の魚たち。たとえ当たり前の普通種であっても、いつも新鮮に感じます。








2016年、石垣島へ移り住むにあたっての不安は、生き物たちとの出会いの感動によって端からなかったもののように払拭され、認識の変容とともに亜熱帯への深い傾倒に変化していきました。その過程を表したのが『黒潮魚の譜』『THE FISH 魚と出会う図鑑』そして『魚へのまなざし −長嶋祐成と大野麥風−』所収の短文「南方の住人」なのですが、それを経て温帯に戻った今、再び自らの内に変化が起ころうとしているのをとても楽しみに感じています。