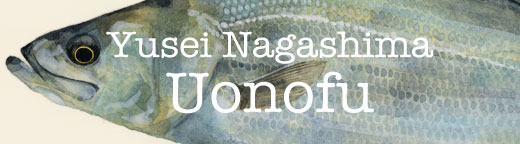アマミ/ナカハラ、タナバタウオ考顛末
ナカハラタナバタウオを狙って伊豆大島に渡った。夜行の大型客船で22時に東京港の竹芝を出て、明朝6時に大島着。潮位が低ければ低いほど狙いやすいので、10:39の干潮(潮位20cm)をクライマックスとして釣り歩き、14時半の船で戻る算段だ。
ナカハラタナバタウオは2021年の夏に一度釣っている。これを狙って八丈島3泊4日の旅程を組み、到着した日の午後早々に釣り上げた。
なぜ既に見ているものをまたわざわざ釣りに行くのか、その説明のためにはアマミタナバタウオという別種に触れなければならない。
タナバタウオというあまり聞き馴染みのない魚は、暖かい海の浅い岩礁域に生息する小型魚のグループで、日本には(タナバタウオ属に限ると)6種が生息している。僕はそのすべてを既に見ているのだけれど、長らく謎めいた存在だったのがアマミタナバタウオという種だった。これは石垣島で2020年には既に釣っており、その後も繰り返し手にしながらも、当時は図鑑にもネットにもアマミタナバタウオとして紹介された生きた姿の写真がほとんど無く、参照することができていなかった。また検索図鑑に載っているアマミの線画や計数形質(ひれのすじなど、数えられる特徴)と突き合わせてみても微妙に一致しない個体が多く、むしろナカハラタナバタウオに近く思えたことから、僕の中では「ナカハラによく似た謎のタナバタウオ」ということになっていた。
この謎を解く手がかりとして、本物のナカハラタナバタウオの方を見ておこうと考えた。ナカハラの主な生息域は沖縄ではなく関東以南の南日本の太平洋岸で、八丈島での釣獲情報があったことから2021年に釣りに行った。そして目論見通り手にしたナカハラは、確かに「謎のタナバタウオ」にとてもよく似た雰囲気を持ちつつも、色や体格に違いがあった。「謎のタナバタウオ」はやはりナカハラではなさそうだ。謎は依然として謎であるということを確かめて、石垣島に戻った。


状況が変わったのはそれから3年も経った2024年のことだった。アマミタナバタウオの論文をオンライン購入したところ、詳しい記述と写真によって「謎のタナバタウオ」はアマミであるとあっさり解けてしまったのだ。この論文の存在は以前から認識していたので、もっと早く購入すればそれで済んでいたのだけれど、恥ずかしながら金額に尻込みしていたのだった。
それ以来、石垣島の旧「謎のタナバタウオ」=アマミタナバタウオは一転してとても身近な存在になったのだけれど、そうなると4年前にただ「謎が謎であること」を確かめるために見に行ったナカハラを、今度はナカハラそのものを理解するために見に行きたい。アマミを理解するための足掛かりとして見たナカハラを、今度はアマミを足掛かりにして見、理解したい。認識の立脚点によって同じものを見ても新たな発見があるということを感じたく、今回の伊豆大島行きを決めた。
また、アマミとナカハラは実際とてもよく似ており、(詳しいことは当然研究者の方々の領分だけれど)両種は日本産タナバタウオ属6種の中でも特に近い関係にあるのではと思っている。
同属の中で亜熱帯と温帯にとてもよく似た種が存在するケースはもう一件思い当たり、それがアカハタ属のヒレグロハタとノミノクチだ。ヒレグロハタは石垣島でよく見かけていた魚なのだけれど、和歌山を旅したときに初めて釣れたノミノクチが、ヒレグロハタの色ちがいであるかのようによく似ているのに驚いた。形だけでなく、体表の質感や釣られたときの姿勢の取り方も近いように思った。
ノミノクチは一般的にキジハタとの類似をよく言われるのだけれど、僕は「亜熱帯のヒレグロハタ/温帯のノミノクチ」というセットで認識している。ここに「亜熱帯のアマミ/温帯のナカハラ」という「タナバタウオセット」を改めて並置することで、亜熱帯と温帯に関する自らの認識に、つまり大袈裟に言えばこの世界の理解の仕方に、また新たな様相が加わることへの期待もあった。


長い前段のようになったけれど、実はここまでの話が本題であって、大島での釣行にはさほど書くほどのこともない。ナカハラタナバタウオは見られずじまいだった。
日本産タナバタウオ属6種はその好む生息環境に違いがあり、八丈島での経験上、ナカハラは潮がやや強めに当たる隙間の多い岩礁(石積みやゴロタなど)を好む。そしてそれは石垣島でアマミが見られるポイントとも共通する環境だと思っている。
だから事前にGoogleマップで大島の海岸線を何周も辿り、期待できそうなポイントをピックアップしておいた。しかし実際に訪れてみると断崖絶壁でアプローチできなかったり、サッカーボール大のゴロタだと思っていたのが人の背丈ほどの大岩だったりで思うようにいかず、「ここで粘ればナカハラが見られる」という確信とともに腰を据えての釣りは最後までできなかった。干潮時刻をとうに過ぎて潮位も上がり、帰りの船の時刻を気にしなければならない頃になって訪れた磯に、八丈島でナカハラを釣ったポイントの雰囲気があったけれど、時既に遅しだった。
ナカハラのためにナカハラを見るのは、また次の機会に持ち越し。こうして空振りに終わった釣行もまた、何らかの形で新たな認識の礎の一部になるに違いない。